毎日、多くの決断と責任のなかで、周囲を牽引し、奮闘されているあなたへ。
「なぜ、これほどまでにストレスが尽きないのだろう…」
「周りの期待に応えなければ。もっと自分が頑張らなければ」
「クライアントや関係者の期待に、120%で応え続けなければならない」
「プライベートも、疎かにはできない…」
そのように、心の中で一人、孤独な戦いを続けてはいませんか?
先日、ある調査で「日本では約半数の人がストレスを感じている」という結果が報じられ、話題になりました。この記事が示す通り、現代日本はまさに「ストレス社会」です。しかし、多くの責任を背負い、日々プレッシャーの中で戦うあなたの肩には、記事に書かれている以上の、計り知れないほどの重圧がのしかかっていることでしょう。
もし、今あなたが抱えているその尽きないストレスや心の重荷が、「実は、あなたが背負う必要のないもの」だとしたら、どう感じますか?
この記事では、自己肯定感の第一人者である私、中島輝が、フロイト、ユングと並ぶ心理学の巨匠アルフレッド・アドラーの「アドラー心理学」の叡智を借りて、あなたの心を蝕むストレスの正体を解き明かします。そして、心の重荷の9割を手放し、自己肯定感を高め、しなやかで折れない心で未来を切り拓くための具体的な方法を、余すところなくお伝えします。
この記事を読み終える頃には、あなたはストレスをただ耐えるものではなく、自らを成長させるための“勇気”の源泉に変えることができるようになっているはずです。
はじめに:なぜ、責任感が強い人ほどストレスを抱え込んでしまうのか?
リーダーが抱える「4つの孤独」と特有のプレッシャー
組織やチームを牽引するあなたは、常に強いリーダーシップを発揮し、周囲を鼓舞する存在でなければならない、そう感じているかもしれません。しかし、その頼もしい姿の裏側で、リーダー特有の「孤独」と戦っているのではないでしょうか。
- 決断の孤独: 最終的な意思決定は、すべて自分一人で行わなければならない。
- 責任の孤独: メンバーの人生や組織の未来、その責任が自分にあると感じる。
- 共感の孤独: 同じ視点、同じ熱量で悩みを分かち合える相手がいない。
- 未来の孤独: 誰も見たことのない未来を、たった一人で見据え続けなければならない。
この「4つの孤独」は、あなたの心に絶えず重くのしかかり、慢性的なストレスの原因となります。責任感が強く、真面目で、誰よりも組織やメンバーのことを考えているあなただからこそ、すべてを一人で抱え込み、心身をすり減らしてしまうのです。
見過ごせない日本のストレス社会の実態
冒頭で触れたように、現代の日本では働く人の約半数が、仕事に関して強いストレスを感じています。これは、もはや社会全体の問題と言っても過言ではありません。
国全体がストレスに覆われる中で、多くの人の未来を背負い、日々プレッシャーと戦うあなたのストレスレベルは、この平均値をはるかに上回っている可能性があります。そして、そのストレスを「リーダーだから仕方ない」「自分の役割だから当然だ」と諦めてしまうのは、あまりにも危険なことなのです。
その不調、燃え尽き症候群(バーンアウト)の危険なサインかもしれません
- 以前は情熱を注げていた仕事に、心が動かなくなった
- 朝、起き上がるのがひどく億劫に感じる
- ささいなことでイライラしたり、感情のコントロールが効かなくなったりする
- どれだけ休んでも、慢性的な疲労感が抜けない
- 仕事のパフォーマンスが著しく低下している
もし、これらのサインに一つでも心当たりがあるなら、それは単なる疲れではなく、燃え尽き症候群(バーンアウト)の前兆かもしれません。バーンアウトは、持続的な職務上のストレスが原因で引き起こされる心身の極度の疲労状態です。一度陥ってしまうと、回復には長い時間と多大なエネルギーを要します。
そうなる前に、今すぐ、あなたのストレスとの向き合い方を根本から見直す必要があるのです。その最強の武器となるのが、アドラー心理学です。
すべての悩みは対人関係?ストレスの根源を断つアドラー心理学の視点

アドラー心理学とは?「勇気の心理学」と呼ばれる理由
アドラー心理学は、オーストリアの精神科医アルフレッド・アドラー(1870-1937)によって創始された心理学です。フロイトの原因論(過去のトラウマが現在の行動を決定する)とは対照的に、アドラーは目的論(人間の行動にはすべて目的がある)を提唱しました。
つまり、「過去に何があったか」ではなく、「これからどうしたいのか」に焦点を当てる、未来志向で実践的な心理学なのです。そして、私たちが困難を乗り越え、幸福な人生を歩むためには「勇気」が必要不可欠であると説いたことから、「勇気の心理学」とも呼ばれています。
衝撃の結論:「人間の悩みは、すべて対人関係の悩みである」
アドラーは、断言しました。
「人間の悩みは、すべて対人関係の悩みである」と。
「いやいや、私の悩みは業績や将来設計であって、対人関係ではない」
そう思われたかもしれません。しかし、アドラー心理学では、一見するとそうは見えない悩みも、突き詰めればすべて対人関係に行き着くと考えます。
- 業績の悩み: 顧客、株主、上司といった「他者」からの評価や信頼を得たいという対人関係。
- 将来設計の悩み: 競合に勝ちたい、社会に貢献したい、家族を幸せにしたいという対人関係。
- 過労による健康不安: 仲間や家族の期待に応えたい、弱みを見せられないという対人関係。
あなたが抱えているストレスも、その根源をたどっていくと、必ず「誰か」の存在が見えてくるはずです。
あなたのストレスを分解する – 部下、顧客、家族、そして「自分」との関係
一度、あなたのストレスの源泉となっている「登場人物」を書き出してみてください。
- 言うことを聞かない部下や後輩
- 無理な要求をしてくるクライアント
- 自分の仕事を理解してくれない家族やパートナー
- 期待する成果を出せない「理想の自分」と「現実の自分」
いかがでしょうか。驚くほど多くの「他者」との関係性の中に、あなたのストレスの原因が潜んでいることに気づくはずです。
アドラー心理学は、これらの複雑に絡み合った対人関係の悩みを、驚くほどシンプルに解決するメスを持っています。それが、次章で詳しく解説する「課題の分離」です。
心の重荷の9割を手放す魔法の思考法「課題の分離」
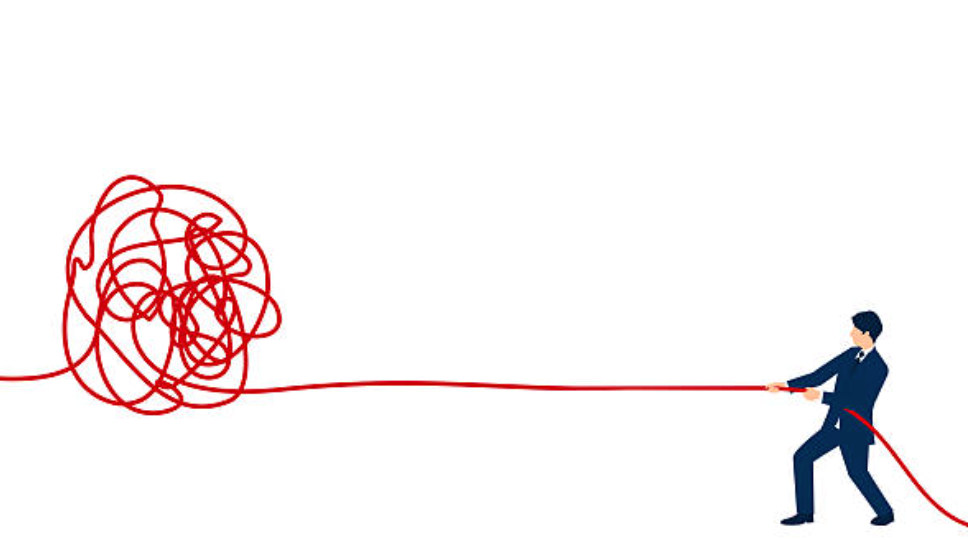
「それは、誰の課題なのか?」この一言があなたを救う
課題の分離とは、文字通り、「自分の課題」と「他者の課題」を明確に線引きすることです。そして、「他者の課題には踏み込まない」と決めることです。
ある問題に直面したとき、自問すべきはたった一つ。
「その選択によってもたらされる結末を、最終的に引き受けるのは誰か?」
この質問の答えが、その課題の持ち主を教えてくれます。
例えば、あなたが部下の仕事の遅さにイライラしているとします。
「部下が仕事を時間内に終える」これは誰の課題でしょうか?
仕事が遅れることで評価が下がり、自身の成長機会を逃すという結末を引き受けるのは、最終的に部下自身です。ですから、これは「部下の課題」です。
あなたは、上司として必要な支援(業務プロセスの見直し、スキルの指導、リソースの提供など)はできます。しかし、最終的にその課題を乗り越えるかどうかは、部下本人が決めること。あなたが彼の課題を肩代わりして、過度に干渉したり、感情的に怒ったり、ましてや彼の分の仕事までやってしまったりするのは、「他者の課題への土足での介入」に他なりません。
この「課題の分離」ができていないと、私たちは他人の課題まで自分のことのように悩み、勝手に背負い込み、不必要にストレスを溜め込んでしまうのです。
【ケーススタディで学ぶ】陥りがちな「課題の混同」
リーダーであるあなたは、責任感の強さから、あらゆることを「自分の課題」だと捉えがちです。具体的なケースで見ていきましょう。
ケース1:部下や後輩がなかなか育たない問題
【よくある悩み】
「手取り足取り教えているのに、部下のAさんが一向に成長しない。私がもっとうまく指導しなければ。組織の成長は私の指導力にかかっている…」
【課題の分離で考えると…】
● あなたの課題: Aさんが成長しやすい環境を整えること。適切なフィードバックや指導を行うこと。業務の権限移譲を検討すること。
● Aさんの課題: 指導を素直に受け止め、自ら学んで成長すること。自分の仕事に責任を持つこと。
あなたがAさんの「成長する」という課題まで背負ってしまうと、「なぜ期待通りに成長しないんだ!」と怒りが湧いたり、「自分の教え方が悪いんだ…」と無力感に苛まれたりします。課題を分離し、「私は私のできる支援をする。どう活かすかはAさん次第」と線引きすることで、あなたは冷静に必要なサポートに集中でき、過度なストレスから解放されます。
ケース2:取引先からの過剰な要求
【よくある悩み】
「主要取引先のB社から、いつも納期ギリギリで無茶な要求が来る。断ったら関係が悪化するかもしれない。なんとかして応えなければ…」
【課題の分離で考えると…】
● あなたの課題: B社との関係性を維持しつつ、自社のリソースで可能な範囲と不可能な範囲を明確に伝え、交渉すること。代替案を提示すること。
● B社の課題: 無茶な要求が通らないのであれば、自社のスケジュールや計画を見直すこと。別の発注先を探すこと。
B社の機嫌を損ねたくない一心で、すべての要求を飲むのは「課題の混同」です。B社が自社の都合で無理を言うのは「B社の課題」。それに対して、あなたがどう対応するかは「あなたの課題」です。毅然と、しかし誠実に「ここまでならできますが、これ以上はできません」と伝えることで、対等で健全なパートナーシップを築くことができるのです。
ケース3:家族からの期待とプレッシャー
【よくある悩み】
「仕事で成功して、親を安心させたい。子供にも立派な親だと思われたい。でも、仕事が忙しくて家族との時間が取れないことに罪悪感を感じる…」
【課題の分離で考えると…】
● あなたの課題: 仕事と家庭のバランスをどう取るか、自分自身の価値観に基づいて決めること。家族と対話し、自分の状況や想いを誠実に伝えること。
● 家族の課題: あなたがどんな人生を歩もうと、それを受け入れ、どう感じるか。
親がどう思うか、子供がどう思うかは、彼らの課題です。あなたがコントロールすることはできません。あなたがコントロールできるのは、自分自身の行動だけ。罪悪感に苛まれるのではなく、「今の私にできるベストは何か?」を考え、行動し、それを誠実に伝える。それで相手がどう思うかは、相手に委ねるのです。
【実践ワーク①】
あなたの「悩み事リスト」を
“課題の分離”で仕分けてみよう
今、あなたが抱えている悩みやストレスを、5つ書き出してみてください。そして、それぞれの悩みについて、「これは誰の課題なのか?」を冷静に分析し、「自分の課題」と「他者の課題」に分けてみましょう。
| あなたの悩み・ストレス | 最終的に結末を引き受けるのは誰? | これは誰の課題? |
|---|---|---|
| 例:部下のAさんが遅刻を繰り返す | Aさん本人 | 他者(Aさん) |
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. |
いかがでしたか? これまで「自分の問題だ」と信じて疑わなかったことの中に、驚くほど多くの「他者の課題」が紛れ込んでいることに気づいたかもしれません。
課題の分離は「冷たい突き放し」ではない。「信頼」と「尊敬」の証
ここで、「課題の分離は、困っている人を見捨てるような、冷たい考え方ではないか?」と感じる方もいるかもしれません。しかし、それは全くの逆です。
アドラーは言います。「他者の課題に介入することこそ、自己中心的で、相手を見下した態度だ」と。
相手の課題を肩代わりするのは、「あなたには、この問題を解決する能力がないでしょう?だから私がやってあげる」という、無意識のメッセージを送っているのと同じです。
本当の意味で相手を勇気づけ、成長を促す関わりとは、「これはあなたの課題だ。あなたにはそれを乗り越える力があると、私は信じている。もし助けが必要なら、いつでも援助する準備がある」というスタンスでいることです。
これは、相手への深い「信頼」と「尊敬」がなければできません。課題の分離とは、相手の自立を心から信じ、見守るという、温かくも力強い「愛」の実践なのです。
なぜ、私たちは他人の課題を背負ってしまうのか?- 低い自己肯定感という壁

「課題の分離」が頭では理解できても、実践するのが難しいと感じる方は少なくありません。その根本的な原因は、多くの場合、自己肯定感の低さにあります。
課題の分離を阻む「承認欲求」という名の呪縛
なぜ、私たちは他者の課題に介入してしまうのでしょうか。その最大の動機の一つが「承認欲求」です。
- 「部下の面倒見がいい、頼れる上司だと思われたい」
- 「無理な要求にも応えてくれる、優秀なパートナーだと認められたい」
- 「家族の期待に応える、立派な人間だと評価されたい」
このように、他者の課題を解決してあげることで、「ありがとう」「すごいね」「助かるよ」といった承認の言葉を得ようとするのです。しかし、アドラーは「承認欲求は不自由な生き方につながる」と警鐘を鳴らします。他者からの承認を追い求める人生は、他人の価値観に振り回され、自分自身の人生を生きられない、いわば「他人の人生を生きる」ことになってしまうからです。
「私がいないとダメだから」- 過剰な責任感の裏にある劣等コンプレックス
「この組織は私がいないと回らない」「この人は私がついていないと何もできない」
一見すると、強い責任感や優しさからくる言葉のように聞こえます。しかし、その深層心理には、「劣等コンプレックス」が隠れている場合があります。
劣等コンプレックスとは、「自分には価値がない」という劣等感を、何らかの形で埋め合わせようとする心の働きです。
「私がいないとダメな状況」を作り出すことで、「他者のお世話をする有能な私」という役割を演じ、自分の価値を実感しようとするのです。これは、相手の自立を妨げ、依存的な関係(共依存)を生み出す危険な罠でもあります。
「見捨てられたくない」- 自己肯定感の低さが引き起こす対人関係の不安
自己肯定感が低いと、心の根底に「ありのままの自分では、誰からも愛されないのではないか」という強い不安(見捨てられ不安)を抱えがちです。
そのため、相手の機嫌を損ねて関係性が壊れることを極度に恐れます。
「ここで断ったら、嫌われてしまうかもしれない」
「期待に応えられなければ、見捨てられてしまうかもしれない」
この不安が、あなたに「課題の分離」を躊躇させ、相手の課題に過剰に踏み込ませるのです。相手の言いなりになることで、一時的に関係性を維持しようとする、いわば「自分を差し出す」ことでしか、対人関係を築けない状態に陥ってしまいます。
このように、自己肯定感という心の土台がグラついていると、アドラー心理学のパワフルな教えも、その真価を発揮することができません。だからこそ、私たちは「課題の分離」と並行して、自己肯定感を育んでいく必要があるのです。
リーダーとしてのあなたの問題解決能力をさらに高めたい場合は、こちらの記事も参考になるでしょう。
▶ アドラー心理学で自己肯定感を高める。人を導くリーダーに必須の「問題解決能力」を鍛える3つの方法
自己肯定感を土台にアドラー心理学を実践する「幸福になる勇気」3ステップ

では、どうすれば自己肯定感という強固な土台を築き、その上で「課題の分離」を実践できるようになるのでしょうか。アドラー心理学では、そのための具体的な3つのステップ「自己受容」「他者信頼」「他者貢献」を示しています。
ステップ1:「自己受容」- 完璧ではない自分を100%受け入れる勇気
自己肯定感の第一歩は、「自己受容」から始まります。
自己受容とは、ポジティブな自分もネガティブな自分も、できている自分もできていない自分も、そのすべてを「これが私だ」とありのままに受け入れることです。
自己肯定というと、「自分はできる!」「自分はすごい!」とポジティブに思い込もうとすることだと誤解されがちですが、それは違います。できない自分にフタをして肯定しようとしても、それは脆い自信にしかなりません。
「60点の自分」にOKを出すことから始めよう
責任感の強いあなたは、常に100点、120点を目指してきたかもしれません。しかし、完璧な人間などどこにも存在しません。
「今は60点しかできない自分」を、「ダメだ」と切り捨てるのではなく、「今は60点なんだな。それでOK」と、ただ事実として受け入れるのです。
大切なのは、変えられないもの(過去や生まれ持った資質など)はそのまま受け入れ、変えられるもの(未来の行動や考え方)に集中する勇気を持つことです。
【簡単チェック】あなたの完璧主義度は?
以下の項目に、いくつ当てはまるかチェックしてみましょう。
- 他人に仕事を任せるのが苦手だ
- 常に「べき思考」(~すべきだ)で物事を考える
- 失敗を極度に恐れ、なかなか行動に移せない
- 自分のやり方や基準に固執してしまう
- 些細なミスでも、自分を激しく責めてしまう
3つ以上当てはまったあなたは、完璧主義の傾向があり、知らず知らずのうちに自分を追い詰めているかもしれません。まずは「完璧でなくてもいい」と、自分自身に許可を出すことから始めてみてください。
ステップ2:「他者信頼」- 裏切りを恐れず、無条件に相手を信じる勇気
自己受容ができ、ありのままの自分にOKを出せるようになると、次のステップである「他者信頼」に進むことができます。
他者信頼とは、相手を信じるにあたって、一切の条件をつけないことです。
「あなたがAをしてくれたら、あなたを信じます」というのは、信頼ではなく「信用」です。銀行がお金を貸すのと同じ、担保や条件付きの関係です。
アドラーの言う「信頼」とは、無条件です。
「部下が期待通りの働きをするかどうかわからない。でも、私は彼/彼女の可能性を信じる」
「取引先が誠実に対応してくれる保証はない。でも、私はパートナーとして彼らを信じる」
このように、裏切られる可能性を恐れずに、まず自分から相手を信じるのです。
もちろん、信じた結果、裏切られることもあるかもしれません。しかし、アドラーはこう言います。
「裏切るかどうかは、相手の課題である。あなたが決めることではない。あなたがすべきことは、自分がどうするかを決めることだけだ」と。
裏切りを恐れて疑心暗鬼になる人生と、裏切られるリスクを覚悟の上で、人を信じる人生。どちらが豊かで、幸福な対人関係を築けるでしょうか。
「課題の分離」とは、この「他者信頼」ができなければ成り立ちません。部下の可能性を信じているからこそ、彼の課題に土足で踏み込まず、彼自身の力で乗り越えることを見守ることができるのです。
ステップ3:「他者貢献」- “貢献感”こそが自己肯定感を育む最大の栄養素
自己受容ができ、他者信頼ができるようになった人がたどり着く最後のステップが「他者貢献」です。
他者貢献とは、仲間である他者に対して、何らかの貢献をすることです。これは、自己犠牲とは全く異なります。むしろ、自分を犠牲にする貢献は、偽りの貢献感しか生みません。
アドラーは、人間は「私は共同体(仲間)にとって有益である」と感じられた時にだけ、自らの価値を実感できると言います。これが「貢献感」です。
重要なのは、その貢献が客観的に見て役に立ったかどうかではありません。
あなた自身が「私は貢献できた」と主観的に感じられることが、何よりも大切なのです。
- メンバーの話を真摯に聞く
- クライアントに感謝の言葉を伝える
- 家族のために食事を作る
どんなに些細なことでも構いません。「自分は誰かの役に立っている」という感覚こそが、承認欲求に頼らない、揺るぎない自己肯定感を育む最大の栄養素となります。
【実践ワーク②】
あなたのリソースで今日からできる
「小さな他者貢献」
あなたが持つリソース(時間、知識、経験、笑顔、言葉など)を使って、今日、誰かのためにできる「小さな貢献」を3つ考えてみましょう。そして、実際に行動に移してみてください。
- 貢献する相手:
できる貢献: - 貢献する相手:
できる貢献: - 貢献する相手:
できる貢献:
行動した後、「自分は役に立てたな」と、その貢献感をじっくりと味わうことを忘れないでください。
アドラー心理学を通じて“本当の自信”を手に入れたい方は、ぜひこちらの記事もお読みください。
▶ 【アドラー心理学で“本当の自信”を手に入れる】自己肯定感を育む6つの力と『嫌われる勇気』の次にすべきこと
共同体感覚へ:ストレスから解放され、真の幸福とリーダーシップを手に入れる

「自己受容」「他者信頼」「他者貢献」という3つのステップは、私たちをアドラー心理学の最終ゴールである「共同体感覚」へと導いてくれます。
アドラー心理学が目指す究極のゴール「共同体感覚」とは何か?
共同体感覚とは、「他者を仲間だとみなし、そこに“自分の居場所がある”と感じられること」です。
ここでいう共同体とは、家庭や会社といった小さな単位から、地域社会、国家、人類、さらには動植物や無機物まで含む、宇宙全体を指します。
この感覚を持つことができれば、私たちは「競争」の世界から抜け出し、「協力」の世界で生きることができるようになります。
- 他者は、自分を打ち負かす「敵」ではなく、共に幸せを目指す「仲間」である。
- 他者の成功は、自分の敗北ではなく、仲間としての「喜び」である。
- 自分は、この広大な共同体の中に、確固たる「居場所」がある。
この感覚を得られたとき、私たちは承認欲求や過度な競争心から解放され、対人関係のストレスは劇的に減少します。
「ここにいてもいい」という絶対的な所属感がもたらす力
リーダーとして、あなたは常に孤独だったかもしれません。しかし、共同体感覚を持つことで、あなたは一人ではないことに気づきます。
メンバーも、取引先も、顧客も、家族も、すべてが同じ目標に向かう「仲間」なのです。
この「ここにいてもいいんだ」という絶対的な所属感、安心感こそが、困難な決断に立ち向かうための尽きない勇気の源泉となります。
リーダーとして、組織を「心理的安全性の高い共同体」にするために
あなたが共同体感覚を育むことは、あなた自身のストレスを軽減するだけでなく、リーダーとして、組織全体に計り知れない良い影響を与えます。
あなたが「課題の分離」を実践し、メンバーを「信頼」することで、彼らは自律的に動き始めます。
あなたが「他者貢献」の姿勢を示すことで、組織内に協力と感謝の文化が生まれます。
その結果、メンバー一人ひとりが「この会社にいてもいいんだ」「自分はここで貢献できている」と感じられる、いわゆる「心理的安全性の高い」組織が生まれるのです。
そのような組織は、メンバーのパフォーマンスを最大化し、イノベーションを生み出し、困難な時代を乗り越える強靭なしなやかさを持つことができます。人前で話すのが苦手な人も、安心して挑戦できるようになるでしょう。
▶ プレゼンが怖いあなたへ|アドラー心理学と自己肯定感で「話すのが苦手な自分」から抜け出す方法
まとめ:ストレスを“勇気”に変え、あなたらしい人生のリーダーになるために

今回は、ストレスに悩むあなたのために、アドラー心理学と自己肯定感の視点から、心の重荷を手放すための具体的な方法をお伝えしてきました。
最後に、重要なポイントを振り返りましょう。
- あなたの悩みの9割は「対人関係」であり、そのストレスの多くは「他者の課題」を背負い込むことから生まれる。
- 「これは誰の課題か?」と問いかけ、「課題の分離」を徹底することで、不要な心の重荷を手放すことができる。
- 「課題の分離」が難しい根本原因は「自己肯定感の低さ」にある。承認欲求や見捨てられ不安が、あなたに他者の課題を背負わせる。
- 真の自己肯定感は「自己受容」「他者信頼」「他者貢献」の3ステップで育まれる。
- 最終ゴールである「共同体感覚」を得ることで、あなたは孤独から解放され、ストレスを“勇気”に変え、真のリーダーシップを発揮できる。
アドラー心理学は、時に厳しく、しかし常に温かい「勇気の心理学」です。
過去の経験や、他人の評価にあなたの価値を決めさせる必要は、もうありません。
あなたは、あなたのままで、すでに価値がある存在です。
この記事でご紹介したワークを、ぜひ今日から一つでも実践してみてください。
小さな一歩が、あなたの世界を、そしてあなたの周りを、より良い方向へと導く大きな推進力となるはずです。
あなたは、組織のリーダーであると同時に、「あなた自身の人生のリーダー」なのです。
ストレスに支配される人生から、自らの勇気で幸福を掴み取る人生へ。
私、中島輝は、あなたがその一歩を踏み出すことを心から応援しています。
あなたの現在の心の状態を、
客観的に知りたくありませんか?
この記事を読んで、ご自身の心と向き合うきっかけが生まれたかもしれません。
しかし、自分一人では気づけない心のクセや、ストレスの根本原因が隠れていることもあります。
まずは、あなたの自己肯定感が今、どのような状態にあるのかを客観的に知ることから始めてみませんか?
簡単な質問に答えるだけで、あなたの心の状態がわかる「自己肯定感チェックテスト」をご用意しました。
このテストを通じて、次の一歩をより明確にするための、貴重なヒントが得られるはずです。
▼今すぐ無料で診断してみる▼【無料】あなたの心の状態がわかる
自己肯定感チェックテスト

自己肯定感の第一人者である中島 輝と共に、自己肯定感の重要性を多くの人に伝えるために活動中。講師としての登壇経験が多く、自己肯定感をはじめとするセラピー・カウンセリング・コーチングの知識が豊富。メディアサイト「自己肯定感ラボ」を通じ、誰もが輝いて生きていくための情報を発信中。

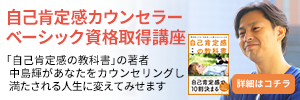
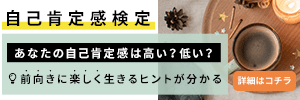
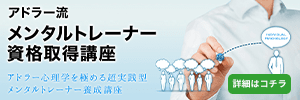
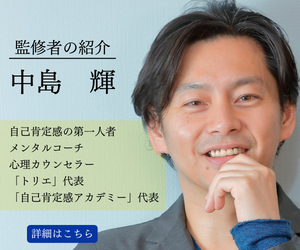
コメント