「今日も、子どもたちとじっくり向き合えなかった…」
「終わらない書類仕事に追われ、気づけば今日もサービス残業…」
「保護者対応や職員会議で、心がすり減ってしまった…」
子どもたちの笑顔が好きで、その成長を支えたいという純粋な想いで選んだ「保育士」という仕事。しかし現実は、理想とはかけ離れた忙しさに追われ、心身ともに疲れ果ててしまっている先生方が、驚くほど多くいらっしゃいます。
「給料が低い」「労働時間が長い」「書類仕事が多すぎる」「職場の人間関係が複雑」といった悩みは、決してあなた一人が抱える特別なものではありません。むしろ、多くの保育士さんが直面している、業界全体の深刻な課題です。
その結果、大好きなはずの子どもたちのささいな言動にイライラしてしまったり、家に帰っても仕事のことが頭から離れなかったり…。そして、ふと「もう、辞めたい…」という言葉が頭をよぎり、そんな自分を責めて自己嫌悪に陥る。そんな悪循環に陥っていませんか?
もし、あなたが今、そんな息苦しさを感じているなら、この記事を最後まで読んでみてください。
この記事は、単なる業務効率化のテクニックを並べたものではありません。自己肯定感の第一人者である私、中島輝が、あなた自身の「心のクセ」に気づき、考え方そのものを変えることで、仕事の負担を劇的に軽くする「アドラー心理学」に基づいた仕事術をお伝えします。
この記事を読み終える頃には、「私が全部やらなきゃ」という思い込みから解放され、心に余裕が生まれ、残業をゼロに近づけ、何よりも大切にしたかった「子どもたち一人ひとりと、笑顔で向き合う時間」を取り戻すための、具体的で力強い一歩が踏み出せるはずです。

1. なぜ、あなたの仕事は終わらないのか?保育士を追い詰める「7つの業務負担」
まず、あなたが「自分の能力が低いから仕事が終わらないんだ」と責めているのなら、その必要は全くありません。
保育士という仕事は、構造的に膨大な業務量を抱えやすい職業なのです。多くの先生方が同じ悩みを抱えています。具体的に見ていきましょう。
1-1. 書いても書いても終わらない「書類・制作物」の無限ループ
指導案、クラスだより、連絡帳、個人記録、保育日誌…。さらに、壁面装飾や誕生日の飾り付けなど、子どもたちが帰った後、静まり返った保育室で一人作業を続ける先生は少なくありません。
1-2. 創造性と体力が求められる「行事準備」のプレッシャー
運動会、発表会など、季節ごとの行事の裏では企画、準備、練習、衣装作りと数ヶ月にわたる膨大なタスクが発生します。成功させなければというプレッシャーも大きく、心身ともに疲弊する大きな要因です。
1-3. ゴールが見えない「会議・研修」の時間
職員会議や各種委員会、研修。どれも必要なものですが、目的が曖昧なまま時間が過ぎたり、勤務時間外に行われたりすることも多く、貴重な時間を奪っていきます。
1-4. 精神をすり減らす「職場の人間関係」と「保護者対応」
女性が多い職場特有の複雑な人間関係や、一部の保護者からの過度な要求やクレーム。チームワークが必須の仕事において、人間関係のストレスは業務効率を著しく低下させます。
1-5. 休憩すらままならない「時間的拘束」
子どもたちの安全を確保するため、お昼寝の時間も連絡帳を書いたりと、実質的な休憩時間が取れないのが現実です。心身をリフレッシュする時間がなければ、午後の保育の質も低下してしまいます。
1-6. 「子どもの命を預かる」という責任の重圧
全ての業務の根底にあるのが、この計り知れない責任の重さです。「絶対に事故を起こしてはいけない」というプレッシャーが、常に先生方の肩にのしかかります。
1-7. これら全てを蝕む「低賃金」という現実
これだけの過酷な労働環境にもかかわらず、給与水準は他の専門職に比べて低い傾向にあります。「頑張りが報われない」という感覚は、仕事へのモチベーションを著しく低下させてしまうのです。

2. 仕事が終わらない本当の理由。それは「心のクセ」にあった
前章で挙げた業務量の多さは、紛れもない事実です。しかし、同じ環境でも、比較的スムーズに仕事をこなし、心に余裕を持って子どもたちと接している先生もいる。その違いは一体どこにあるのでしょうか。
その答えは、単なる能力や経験の差だけではありません。長年の間に無意識に身につけてしまった、仕事に対する「考え方」や「心のクセ」に、本当の理由が隠されているのです。
2-1. 問題の根源は「完璧主義」と「過剰な責任感」
「指導案は完璧に書かなければ」「壁面は誰よりも綺麗に作らなければ」「保護者の期待に120%で応えなければ」。
真面目で責任感の強い先生ほど、この「完璧主義」の罠に陥りがちです。そして、「私がやらなきゃ、この子たちがかわいそう」「私が休んだら、みんなに迷惑がかかる」という過剰な責任感が、自分を犠牲にすることを「当たり前」だと思わせてしまいます。
2-2. あなたを縛る心の声に気づく
あなたの頭の中で、こんな声が聞こえませんか?
- 「~べきだ」(もっと頑張るべきだ、笑顔でいるべきだ)
- 「どうせ私なんて…」(どうせ私がやっても評価されない)
- 「もし~だったらどうしよう」(もし失敗したら、保護者からクレームが来たら…)
これらのネガティブな「心の声」が、あなたから行動の自由を奪い、一つの仕事に過剰な時間をかけさせ、新しい挑戦への勇気をくじいてしまうのです。
2-3. 根底にあるのは「自己肯定感の低下」
そして、これらの「心のクセ」の根っこにあるのが、「自己肯定感の低下」です。自己肯定感とは、「ありのままの自分を、かけがえのない存在として認め、受け入れる感覚」のこと。
この心の土台が揺らいでいると、他人の評価に振り回され、自分を信じることができず、常に不安や罪悪感に苛まれてしまいます。
では、なぜ保育士という仕事は、これほどまでに自己肯定感が下がりやすいのでしょうか。次の章で、その構造的な問題について詳しく見ていきましょう。
3. あなたのせいじゃない。保育士の自己肯定感が下がりやすい「4つの構造」
「自己肯定感が低いのは、私の心が弱いからだ…」もしあなたがそう思っているなら、それは大きな間違いです。保育の現場には、どんなに強い心を持った人でも自己肯定感が削られてしまいやすい、特有の「構造」が存在するのです。
自己肯定感が下がる4つの構造
① 減点評価の環境
保育の仕事は、「できて当たり前」と見なされがち。褒められる機会は少なく、ヒヤリハットや小さなミスといった「マイナス点」だけが目立ってしまいます。
「失敗してはいけない」という恐怖が、「ありのままの自分」を否定する気持ちを育てます。
② 感情労働のすり減り
常に穏やかで、笑顔の「理想の先生」を演じ続ける感情労働。本当の感情に蓋をし続けると、「素の自分」と「演じている自分」のギャップに苦しみ、「本当の私はダメだ」と自分を責めるようになります。
③ 他者評価への依存
「〇〇先生はすごいのに私は…」と同僚と比較したり、保護者の評判に一喜一憂したり…。自分の価値を「他人の目」で測っているうちは、心の安定は得られず、常に他人の顔色をうかがってしまいます。
④ 「貢献感」の欠如
自己肯定感の重要な柱である「貢献感」。しかし、低い給与や長時間労働などで「頑張りが報われない」と感じると、「こんなに頑張っているのに何の意味があるの?」という無力感に襲われ、自己肯定感は根底から揺らぎます。
これらの構造を理解すれば、あなたが今感じている辛さが、決してあなた一人のせいではないことがわかるはずです。
では、この状況をどう乗り越えればいいのでしょうか。その強力な武器となるのが、次の章でお伝えするアドラー心理学のマインドセットです。
4. 【心構え編】アドラー心理学で仕事観が変わる!残業ゼロへのマインドセット3箇条

「課題の分離」や「貢献」の意味がわかっても、すぐに実践するのは難しいかもしれません。そこで、明日からあなたの心に留めておいてほしい「3つの勇気」をご紹介します。
条文1:「100点満点」ではなく「60点の及第点」を目指す勇気
完璧主義を手放しましょう。保育の安全が守られ、子どもたちが楽しく過ごせるという60点の及第点をクリアすればOK、と自分に許可を出してみてください。壁面飾りが少し曲がっていても、子どもたちの笑顔はなくなりません。
条文2:「できないこと」を正直に伝え、助けを求める勇気
「一人で抱え込む」のはやめましょう。「手伝ってもらえませんか?」と正直に伝えることは、無能の証明ではありません。むしろ、チームとして成果を出すための、極めて合理的なコミュニケーションです。
助けを求めることは、他者を「信頼」し、「貢献の機会」を与える行為でもあります。
条文3:「嫌われること」を恐れず、自分の意見を言う勇気
アドラーは言います。「すべての人から好かれようとすることは、不可能なだけでなく、不自由な生き方だ」と。会議で非効率な慣習に意見を言う。
それによって相手がどう思うかは「相手の課題」です。「嫌われる勇気」を持つことで、あなたは不必要な仕事とストレスから解放されます。
5. 【実践編】明日からできる!子どもと向き合う時間を生み出す超・業務効率化術5選
マインドセットが整ったら、具体的なテクニックでさらに仕事のスピードを上げていきましょう。アドラー心理学の考え方をベースに、明日からすぐに試せる業務効率化術です。
💡 5-1. 【書類仕事】「探す時間」をゼロに。テンプレート化とICT導入のすすめ
指導案、クラスだより等のフォーマットを一度作り、使い回しましょう。手書きをPC作成に切り替えるだけで修正は容易に。保育士向けアプリやクラウドサービスで書類データを一元管理すれば、探す時間がなくなります。
💡 5-2. 【制作物】「持ち帰り仕事」撲滅!「やめることリスト」を作る
「本当にこれは必要か?」と自問自答し、「やめること」「簡略化すること」をリストアップ。「壁面は子どもたちの絵をそのまま飾る」「誕生カードは既製品も活用する」など、完璧主義を手放しましょう。
💡 5-3. 【時間管理】「緊急度と重要度」のマトリクスで仕事に優先順位をつける
仕事を「重要かつ緊急」「重要だが緊急でない」「緊急だが重要でない」「重要でも緊急でもない」の4つに分類。
本当に時間をかけるべきは「重要だが緊急でない」仕事です。一日の始めにタスクを整理するだけで行動の質が変わります。
💡 5-4. 【会議】「目的とゴール」を明確化し、ダラダラ会議を終わらせる
会議の「目的は何か?」「何が決まれば終わりか?」を常に意識しましょう。アジェンダを事前に共有し、時間を区切る。「〇分で結論を出しましょう」と提案する勇気も大切です。
💡 5-5. 【掃除・雑務】「分担と同時進行」で、すきま時間を最大限に活用する
掃除や片付けは、保育時間中に子どもたちと一緒に。「お片付け競争しよう!」など遊びの要素を取り入れれば、教育活動にもなります。「おもちゃの消毒」と「明日の準備」など、複数の雑務を同時進行できないか考えましょう。
6. 職場の人間関係が驚くほど楽になる「課題の分離」コミュニケーション術
業務効率化の最大の障壁ともいえる「人間関係」。ここでも「課題の分離」は絶大な効果を発揮します。
6-1. 先輩・同僚との関係:「べき思考」を手放し、健全な協力関係を築く
「後輩は先輩の言うことを聞くべきだ」といった「べき思考」は、人間関係をこじらせる原因です。相手のやり方を尊重しつつ、自分の意見は「I(アイ)メッセージ」で伝えましょう。
「(あなたは)どうしてこうしないの?」ではなく、「私はこうすると、もっとスムーズに進むと思うのですが、いかがでしょうか?」と提案するのです。
6-2. 保護者との関係:過度な要求に「NO」を伝え、信頼関係を深める
理不尽な要求やクレームに、何でも受け入れる必要はありません。まずは相手の気持ちに共感を示し(「ご心配だったのですね」)、その上で、園の方針として「できること」と「できないこと」を冷静に、しかし毅然と伝えましょう。誠実な態度は、長い目で見て必ず信頼に繋がります。
6-3. あなたは一人じゃない。悩みを共有できる仲間を見つけよう
アドラー心理学の「共同体感覚」は、職場だけでなく、より広い範囲で感じることができます。職場の同僚、同期、あるいは外部の研修で知り合った保育士仲間など、本音で悩みを分かち合える存在は、あなたの心を支える大きな力になります。
▼ 関連記事はこちら ▼
保育士の先生方と同じように、心身をすり減らしやすい看護師の方々へ向けた記事も、あなたの悩みを軽くするヒントになるはずです。
→ 【看護師さん、本当にお疲れさまです】「もう疲れた…」心がすり減る毎日に。アドラー心理学&自己肯定感でフッと心が軽くなる3つのヒント
職場の人間関係に特化して悩んでいるなら、「課題の分離」をさらに深く解説したこの記事が、具体的な処方箋となるでしょう。
→ 【中島輝 監修】看護師の人間関係は“課題の分離”で9割解決!自己肯定感を育むアドラー心理学の処方箋
保護者や同僚とのコミュニケーション、特に初対面の人と話すのが苦手だと感じるなら、自信を持って話せるようになるヒントがここにあります。
→ 「もう緊張しない」初対面でも自信を持って話せるようになる方法【自己肯定感×アドラー心理学で変わるコミュニケーション】
7. 【最後に】自己肯定感を取り戻し、あなたらしい保育士になるために

毎日、本当にお疲れさまです。
仕事が終わらないのは、決してあなたの能力が低いからではありません。構造的な問題と、「完璧でありたい」と願うあなたの優しさ、そして責任感の強さが、あなた自身を追い詰めていただけなのです。
アドラー心理学の「課題の分離」は、冷たい考え方ではありません。むしろ、自分と相手を尊重し、信頼するための温かい知恵です。
あなたが自分の課題に集中し、心身ともに健康でいること。それこそが、子どもたち、保護者、そして職場全体への、最高の貢献なのです。
業務効率化は、仕事を機械的にこなすためではありません。それは、あなたが心から大切にしたい「子どもたちと心を通わせる時間」「一人ひとりの成長をじっくり見守る時間」という、かけがえのない宝物を手に入れるための手段です。
自分を責めるのをやめて、まずは一つ、できそうなことから試してみてください。あなたの自己肯定感が高まれば、見える世界は必ず変わります。
あなたらしい笑顔で、子どもたちと向き合える毎日が訪れることを、心から応援しています。
その知恵を、本物のスキルへ。
あなた自身と、周りの人を輝かせる専門家になりませんか?
この記事でご紹介したアドラー心理学の考え方に触れ、「もっと深く学んでみたい」「この知恵を、自分のためだけでなく、同僚や保護者、そして子どもたちのために活かしたい」と感じた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
アドラー流メンタルトレーナー資格取得講座
この講座では、アドラー心理学の理論を体系的に学び、人間関係や仕事の悩みを根本から解決し、自己肯定感を育むための具体的なスキルを習得できます。あなた自身の働き方が劇的に変わるだけでなく、悩める仲間を支え、保護者との信頼関係を築き、子どもたちの「生きる力」を育む専門家としての新たな道が拓けます。
200回を超え、歴史と実績のあるこの機会に、あなたも新しい一歩を踏み出してみませんか?
残業ゼロの先にある、あなたらしい輝くキャリアを、ここで手に入れてください。▶︎ 講座の詳細を今すぐ見てみる

自己肯定感の第一人者である中島 輝と共に、自己肯定感の重要性を多くの人に伝えるために活動中。講師としての登壇経験が多く、自己肯定感をはじめとするセラピー・カウンセリング・コーチングの知識が豊富。メディアサイト「自己肯定感ラボ」を通じ、誰もが輝いて生きていくための情報を発信中。

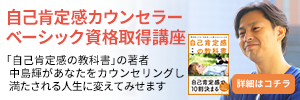
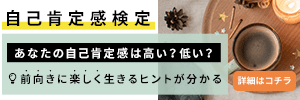
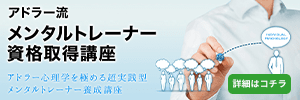
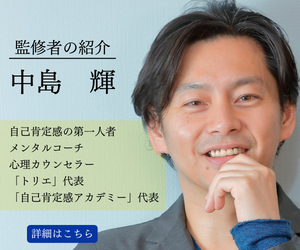
コメント