「また、いない…」
静まり返った深夜に響く、自分の心臓の音。
冷たい汗が、パジャマを湿らせて背中を伝っていくのを感じます。
家中を探し回り、かすかな物音に耳を澄まし、それでも見つからなかった時の絶望感。
近所迷惑もかえりみず、震える声で名前を呼びながら夜道を歩く時間は、まるで永遠のように長く、心を鋭利な刃物でえぐられるような感覚に陥ります。
警察に連絡し、無事を祈りながら夜が明けるのを待つ間、頭をよぎるのは「どうして私だけがこんな目に…」という、やり場のない怒りと悲しみ。
そして、そんな風に思ってしまう自分自身への、耐えがたいほどの罪悪感…。
この記事を読んでくださっているあなたは、今まさに、そんな出口の見えないトンネルの中で、たった一人で光を探し、戦っているのかもしれません。
認知症による「徘徊」と呼ばれる行動は、介護をする家族の体力をじわじわと奪うだけでなく、心を少しずつ、しかし確実に蝕んでいく、非常に過酷な症状です。
「もう限界だ」と心が悲鳴を上げるのは、決してあなたが弱いからでも、愛情が足りないからでもありません。
どうか、それだけは忘れないでください。
こんにちは。自己肯定感の第一人者、中島輝です。
これまで、本当に多くの介護者の方々のカウンセリングを行ってきましたが、皆さんが共通して抱えているのが、この「先の見えない不安」と「自分を責め続けてしまう苦しみ」です。
しかし、どうか安心してください。
この記事では、認知症の徘徊に悩むあなたが、明日から少しでも心が軽くなるための具体的な知識と方法を、どこよりも分かりやすく、そしてあなたの心に寄り添いながらお伝えします。
徘徊の原因と対応策といった一般的な情報はもちろんのこと、この記事でしかお伝えできない「介護者自身の自己肯定感を守る方法」、そして、変わりゆく親の姿への言葉にならない悲しみと向き合う「グリーフケア」という、新しい光の当て方をお伝えします。
この記事を読み終える頃には、あなたはもう一人ではありません。
暗闇に差し込む温かい光を見つけ、自分自身を大切にする許可を出しながら、再び前を向く力を取り戻しているはずです。
それは「徘徊」ではなく「目的のあるお出かけ」。認知症の方が見ている世界

私たちがつい「徘徊」と呼んでしまう、あのあてもなく歩き回っているように見える行動。
でも、もし、ご本人にとってはそれが、決して意味のない行動ではなく、とても切実な理由や目的を持った「お出かけ」なのだとしたら、私たちの見方は少し変わるかもしれません。
この、ほんの少しの視点の転換こそが、対応の第一歩であり、追い詰められたあなたの心を、ふっと軽くしてくれるきっかけになるのです。
では、一体どんな理由が、ご本人を「お出かけ」へと駆り立てるのでしょうか。
ここでは、その行動の裏に隠された、ご本人の心の世界を一緒に、そっと覗いてみたいと思います。
1-1. なぜ?その一歩に隠された、5つの切実な想い
認知症の方の、一見すると不可解に見える行動には、必ずご本人なりの理由が存在します。
それは、私たちには理解しがたいかもしれませんが、ご本人にとっては至極まっとうな、心の叫びなのです。
その声に耳を澄ませてみましょう。
1-1-1. 「ここはどこ?」見慣れた景色が歪む、見当識障害の不安
認知症の代表的な症状の一つに、時間や場所、人がわからなくなってしまう「見当識障害」というものがあります。
これは、まるで霧の中でコンパスを失ってしまったような状態です。
何十年と住み慣れた我が家でさえ、ある日突然、「ここは自分の家ではない、見知らぬ場所だ」と感じてしまうことがあります。
そうなると、ご本人の中で芽生えるのは、「早く安心できる本当の家に帰らなくては」という、強い焦りと不安です。
その必死の想いが、玄関のドアに手をかけさせるのです。
【ご本人の心の声】
「なんだか、いつもと壁紙の色が違う気がする…。ここは私の家じゃないわ。早く家に帰らないと、家族が心配してしまう…」
1-1-2. 心が休まらない…不安やストレスからの逃避行
環境の変化は、私たちが想像する以上に、認知症の方の心に大きな波紋を広げます。
例えば、引っ越しや入院、デイサービスの利用開始といった出来事は、大きなストレスの原因となります。
また、私たち家族が良かれと思ってかけた言葉や、ついイライラしてしまった時の険しい表情も、ご本人を不安にさせてしまうことがあります。
静かすぎる環境も、逆に騒がしすぎる環境も、落ち着かない原因になり得ます。
そんな「ここにいたくない」という居心地の悪さから逃れるために、ただ安心できる静かな場所を求めて、外へと足が向かってしまうのです。
【ご本人の心の声】
「なんだかここは騒々しくて落ち着かないな…。息子夫婦が喧嘩しているみたいで怖い…。どこか、静かなところへ行きたい…」
1-1-3. 「会社へ行かなきゃ」身体に刻まれた、愛おしい過去の習慣
ご本人の中では、時計の針が、何十年も前に戻っていることがあります。
毎朝同じ時間に起きてネクタイを締め、会社へ向かった日々。
夕方になれば、子供を幼稚園に迎えに行くのが日課だった頃。
その、長年かけて身体に染みついた大切な習慣が、ふとした瞬間に蘇ってくるのです。
それは、ご本人にとっては今まさに果たさなければならない「使命」であり、責任感に満ちた行動です。
周りから見れば奇妙に映るかもしれませんが、その心は、家族のために懸命に生きてきた、誇り高い過去の姿そのものなのです。
【ご本人の心の声】
「大変だ、もうこんな時間か!早く会社に行かないと、大事な会議に遅れてしまう。部長に叱られてしまうぞ」
1-1-4. 言葉にならない体のサイン。痛みや不快感の訴え
頭が痛い、お腹が気持ち悪い、喉が渇いた、トイレに行きたい。
私たちが当たり前に言葉にできる体の不調や欲求を、認知症の方はうまく表現できなくなることがあります。
その言葉にならない不快感を、なんとか自分で解決しようとして、トイレを探し回ったり、昔よく通った売店を探しに行こうとしたりします。
それは、助けを求める、声なきサインなのかもしれません。
【ご本人の心の声】
「トイレはどこだったかな…。お腹がぐるぐるして気持ちが悪い…。誰にも言えないけど、どうにかしたい…」
1-1-5. 薬の影響や「せん妄」という、一時的な心の混乱
いつも飲んでいるお薬の副作用によって、頭がぼんやりしたり、足元がふらついたりして、意図せず外に出てしまうことがあります。
また、熱を出したり、脱水症状になったり、環境が急に変わったりしたことをきっかけに、「せん妄」という一時的な意識の混乱状態に陥ることもあります。
その際、幻覚が見えたり、興奮したりして、パニック状態で外に飛び出してしまうケースも少なくありません。
もし、急に行動のパターンが変わったと感じたら、それは専門家への相談のサインです。
一人で抱え込まず、まずはかかりつけのお医者様に相談してみてください。
【ご本人の心の声】
「なんだか頭がぼーっとする…。虫がたくさん壁を這っているのが見える…怖い、ここから逃げ出さないと…!」
「ダメ!」は心を閉ざす言葉。徘徊が起きた時のNG対応と、心をつなぐOK対応

「どこに行くの!」「また勝手に出ていって!」。
必死に探した後の焦りや疲れから、つい強い言葉で本人を責めてしまう。
そのお気持ちは、痛いほどわかります。
しかし、その対応が、ご本人の心を固く閉ざさせ、さらなる混乱を招いてしまうとしたら…?
ここでは、ご本人の心を傷つけることなく、状況を穏やかに収めるための関わり方を一緒に学んでいきましょう。
2-1. 【NG対応】良かれと思って…でも心を傷つけてしまう3つの行動
追い詰められた状況で、私たちはつい、ご本人をコントロールしようとしてしまいます。
しかし、その行動が逆効果になってしまうことがあるのです。
一つ目は、頭ごなしに否定したり、叱ったりすることです。
「行っちゃダメ!」「何言ってるの、会社はもう定年したでしょ!」といった言葉は、ご本人にとっては、自分の存在そのものを否定されたように感じてしまいます。
それは深い悲しみや怒りを生み、「この人には何も話せない」と心を閉ざしてしまう原因になります。
二つ目は、力ずくで止めようとすること。
腕を強く掴んだり、無理やり家に連れ戻そうとしたりする行動です。
ご本人は「攻撃された」と感じ、恐怖から抵抗してしまい、転倒などの思わぬ事故につながる危険性があります。
介護しているあなた自身が、怪我をしてしまうかもしれません。
そして三つ目は、鍵をかけて閉じ込めてしまうこと。
これは、ご本人の尊厳を著しく傷つける行為であり、強い恐怖と孤独感を与えます。
また、火災や地震などの緊急時に逃げ遅れるという命の危険にも直結するため、絶対に行ってはいけません。
2-2. 【OK対応】本人の尊厳を守る、魔法の5ステップ
ご本人が外に出ようとしている場面に出会ったら、焦る気持ちを一度脇に置いて、これからお伝えする5つのステップを思い出してみてください。
驚くほど、ご本人の表情が和らぎ、心が通じ合う瞬間が訪れるかもしれません。
ステップ1:まずは心を落ち着かせ、見守る
「またか…」と焦る気持ちで胸がいっぱいになると思いますが、まずはご自身の心のために、ゆっくりと一つ深呼吸をしてみましょう。
そして、危険がない限りはすぐに止めようとせず、ご本人が何をしようとしているのか、どこへ行こうとしているのかを、そっと見守ります。
ステップ2:共感し、理由を尋ねる(傾聴)
次に、ご本人と同じ目線の高さまでかがみ、優しい声で話しかけてみてください。
「お出かけですか?」「どちらまで行かれるんですか?」と。
もし「会社に行くんだ」と答えが返ってきたら、決して否定せず、「そうなんですね、お仕事ですか。いつもお疲れ様です」と、まずはそのお気持ちを丸ごと受け止めてあげましょう。
ステップ3:気持ちを逸らし、提案する(代替案)
ご本人の目的を受け止めてあげた上で、自然な形で関心を別の方向に向けてみます。
「会社に行かれるんですね。でも、お腹が空きませんか?お茶でも一杯飲んでからにしませんか?」あるいは、「お迎えですね。まだ少し時間があるみたいなので、一緒にテレビでも見ながら待ちませんか?」というように。
ポイントは、ご本人の世界観を尊重した上で、次の行動を優しく提案してあげることです。
ステップ4:一緒に行動する
それでもどうしても外に出たいという気持ちが強い場合は、無理に引き留めるのではなく、安全を確認しながら少しだけ付き添ってあげるのも素晴らしい対応です。
玄関先まで出て外の空気を吸ったり、近所を少しだけ散歩したりするだけで、ご本人の気持ちが落ち着き、満足して家に戻ってくれることはよくあります。
ステップ5:安心できる言葉をかける
「大丈夫ですよ」「私がそばにいますからね」「心配いりませんよ」。
これらの言葉は、徘徊の根底にある強い「不安」を和らげる、何よりのお薬です。
あなたが味方でいてくれること、一人ではないことを伝え続けることが、ご本人の心を穏やかにする一番の近道なのです。
2-3. コラム:この症状はいつまで続くの?希望の光について
終わりの見えない徘徊に、「これが一生続くのか…」と絶望的な気持ちになってしまうかもしれません。
しかし、徘徊は認知症の進行度合いや、環境、体調によって波があります。
一般的に、アルツハイマー型認知症の中期に最も症状が強く現れると言われていますが、環境が安定したり、ご本人が安心できる関わり方が見つかったりすることで、症状が落ち着いてくるケースも少なくありません。
どうか希望を捨てずに、今できることに一つずつ取り組んでいきましょう。
徘徊の不安を減らすために。今日からできる、具体的な7つの予防という優しさ

徘徊が起きてから対応する体力や気力は、毎日すり減っていきます。
だからこそ、そもそも徘徊が起きにくい環境や関わり方という「予防」の視点が、あなたとご家族の穏やかな毎日を守るためにとても大切になります。
ここでは、今日から実践できる具体的な予防策を、優しさという視点からご紹介します。
3-1. 「ここにいたい」と思える、安心できる”居場所”づくり
ご本人が「ここにいるのが一番落ち着くな」と感じられる環境づくりが、何よりも大切です。
昔から使い慣れた家具や、懐かしい家族の写真、大切にしていた趣味のものを目に見える場所に飾るだけで、そこは安心できる”ご本人の居場所”になります。
また、トイレの場所が分からず探し回ることがきっかけになることも多いため、ドアに「便所」と大きな紙を貼ったり、夜間も廊下の電気をつけたりする工夫も、不安を取り除く優しい配慮です。
3-2. 太陽のリズムで暮らす。心地よい眠りのための日中の過ごし方
昼と夜の区別がつかなくなる昼夜逆転は、夜間徘徊の大きな原因の一つです。
朝になったらカーテンを開けて太陽の光を浴び、日中は散歩や庭いじり、デイサービスでのレクリエーションなど、少しでも体を動かす機会を作りましょう。
心地よい疲労は、夜の穏やかな眠りへと繋がっていきます。
3-3. 心の不安を取り除く、日々のコミュニケーションというお薬
日頃からの何気ない会話が、ご本人の不安を和らげ、徘徊の気持ちを芽生えさせないためのお薬になります。
ご本人の話を、たとえ辻褄が合わなくても、否定せずに「そうなんだね」と耳を傾けてあげてください。
そして、「洗濯物をたたむのを手伝ってくれる?」「お皿を拭いてもらえると助かるわ」といった簡単な役割をお願いすることも、ご本人の「自分はまだ役に立てる」という自己肯定感を支える、大切な関わり方です。
3-4. もしもに備えるテクノロジー。介護者の心を軽くするお守り
万が一の時に備えて、便利な機器の力を借りることは、決して悪いことではありません。
それは、あなたの心を少しだけ軽くしてくれる、大切なお守りになります。
靴やカバンにそっと忍ばせられる小型のGPS端末や、玄関や窓が開くとスマートフォンに知らせてくれる人感センサーなど、様々なものがあります。
3-5. 地域全体で見守る温かい目。「SOSネットワーク」への登録
多くの自治体では、認知症の人が行方不明になった際に、地域の様々な機関が連携して早期発見に協力してくれる「見守りSOSネットワーク(名称は自治体により異なります)」という仕組みがあります。
一人で抱え込まず、地域社会の力を借りることも考えてみてください。
お住まいの市区町村の高齢者福祉担当課や、地域包括支援センターで相談できます。
3-6. 服や持ち物にそっと忍ばせる、”あなた”と繋がる情報
もしもの時に備え、ご本人の身元がわかる情報を身につけてもらうことも、安心に繋がります。
衣類やカバンに名前と連絡先を書いた名札を縫い付けたり、自治体が配布しているQRコード付きのシールを活用したりと、ご本人が嫌がらない形で工夫してみましょう。
3-7. 警察は最後の砦ではない。もしものための事前相談
警察は、行方不明になってから頼るだけの場所ではありません。
あらかじめ最寄りの警察署や交番に、行方不明になる可能性があることを相談し、本人の名前や特徴、写真などを登録しておくことができます。
この事前のひと手間が、万が一の際の迅速な対応に繋がるのです。
【この記事の核心】介護者自身の心が壊れる前に。あなたを救う「自己肯定感」

さて、ここまで徘徊への具体的な対応策をお伝えしてきました。
しかし、この記事で私が最もあなたにお伝えしたいこと。
それは、介護をしている「あなた自身」の心を守ることです。
どんなに素晴らしい介護のテクニックを学んだとしても、あなたの心が疲弊し、壊れてしまっては、すべてが意味をなさなくなってしまいます。
認知症介護は、介護者の自己肯定感をじわじわと、しかし確実に奪っていく、あまりにも過酷な道のりなのです。
4-1. なぜ介護は心をすり減らすのか?「3つの感情」の正体
介護をしていると、どうしても自己肯定感を失いやすくなります。
それは、主に3つの重く、苦しい感情に心が支配されやすくなるからです。
一つ目は「罪悪感」です。「もっと優しくできれば…」と自分を責める気持ち。
ついイライラして声を荒らげてしまった後、「なんて酷いことを言ってしまったんだろう」と自分を責める。
徘徊する親に対して「いなくなればいいのに」と一瞬でも思ってしまった自分に嫌悪感を抱く。
この罪悪感が、あなたの自己肯定感を最も深く傷つけます。
二つ目は「無力感」。「何をしても良くならない」という絶望です。
一生懸命に対応しても、徘徊はなくならない。症状は日に日に進んでいくように見える。
「私の努力はすべて無駄なんだ」という無力感は、やがて介護への意欲そのものを静かに奪っていきます。
そして三つ目が「孤独感」です。「この辛さを誰もわかってくれない」という孤立した感覚。
友人や親戚に相談しても、「大変ね」の一言で終わってしまう。
社会から切り離され、たった一人でこの重荷を背負っているという孤独感は、あなたの心を冷たく、硬くしていきます。
これらの感情を抱くのは、あなたが弱いからではありません。
それだけあなたが、真剣に、誠実に、介護と向き合っている、何よりの証拠なのです。
だから、まずはそんなご自身を「今日まで、本当によく頑張ってきたね」と、認めてあげることから始めてみませんか。
4-2. 罪悪感・無力感・孤独感の嵐に飲み込まれないために
ネガティブな感情の嵐に飲み込まれそうになった時、それに必死に抗うのではなく、少しだけ客観的に眺めるための心の技術があります。
一つは「感情のラベリング」です。
「あ、今、私『罪悪感』を感じているな」「『無力感』の波が来ているな」と、自分の感情にそっと名前をつけてみてください。
これだけで、感情と自分との間に少し距離が生まれ、感情の渦に巻き込まれにくくなります。
もう一つは「事実と感情の切り離し」です。
「(事実として)親が徘徊した」ことと、「(感情として)私がダメだからだ」という考えを、意識的に切り離してみましょう。
「徘徊は病気の症状であって、私のせいではない」と、冷静に事実だけを捉える練習をすることで、過剰に自分を責める思考の癖から、少しずつ自由になれるはずです。
4-3. 【簡単ワーク】1日5分、自分と向き合う。心を最優先する「セルフコンパス」の時間
介護者のための自己肯定感を育むセルフコンパス・ワーク
私たちは、つい親のことばかりを考え、自分のことを後回しにしがちです。
しかし、あなたが倒れてしまっては、共倒れです。
1日にたった5分でいいのです。意識的に、あなたのためだけの時間を作ってあげてください。
- 静かな場所で一人になる
(トイレやお風呂、布団の中など、どこでも構いません) - 胸に優しく手を当てて、深呼吸を3回する
「吸って…吐いて…」自分の体の感覚に、そっと意識を向けてみましょう。 - 自分に3つの質問を、優しく投げかける
- 「今日の私、どんな気分?」
(例:イライラしてる、悲しい、疲れた…どんな感情も否定せず、「そう感じているんだね」と、ただ受け止めてあげましょう) - 「今日の私、本当はどうしたかった?」
(例:ゆっくり眠りたかった、甘いものが食べたかった、一人になりたかった…その心の声を、ただ聞いてあげましょう) - 「そんな頑張ってる私に、どんな言葉をかけてあげたい?」
(例:いつもありがとう、よくやってるよ、無理しないでね、完璧じゃなくていいんだよ…あなた自身が、あなたの一番の味方になってあげてください)
- 「今日の私、どんな気分?」
このワークは、自分自身の心の声に耳を傾け、自分を労わるための大切な時間です。
これを続けることで、すり減ってしまった自己肯定感が、温かいスープのように、少しずつ心に染み渡っていくのを感じられるはずです。
4-4. 「完璧な介護」という、あなたを苦しめる呪いを解くために
100点の介護を目指す必要は、どこにもありません。
60点で十分なのです。時には30点の日があったっていい。
0点の日があったって、あなたは決してダメな人間ではありません。
「完璧な介護」という幻想は、あなたを苦しめる呪いになります。
それよりも、「まあ、今日はこれだけできたからOK」「今日はもう無理だから休もう」と、自分に許可を出せる「そこそこの介護」を目指しましょう。
その方が、結果的に長く、穏やかに介護を続けることができるのです。
変わりゆく親への悲しみと向き合う。「予期グリーフケア」という光
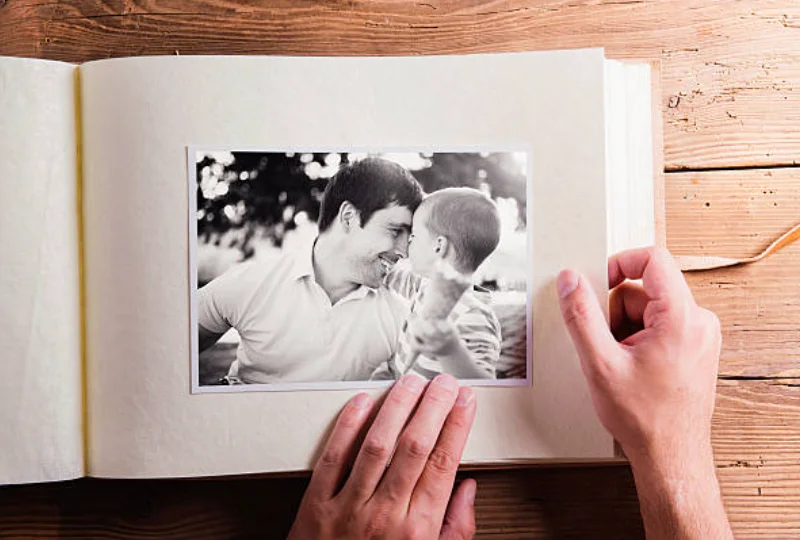
徘徊する親の姿を見て、あなたはもう一つ、別の種類の、言葉にしがたい深い悲しみを感じているかもしれません。
「昔はあんなにしっかりしていたのに…」
「もう、昔のお母さん(お父さん)はどこにもいない…」
これは、単なる介護疲れとは質の違う、胸が締め付けられるような「喪失感」です。
私たちは、愛する人が亡くなった時だけに悲しみを感じるわけではありません。
認知症によって、その人らしさが少しずつ失われていく過程でも、同じように、あるいはそれ以上に複雑で深い悲しみ(グリーフ)を経験するのです。
この、「生きている相手に対して抱く喪失感」を、私たちは「予期グリーフ」と呼んでいます。
5-1. 「昔の親はもういない…」その悲しみには、ちゃんと名前があるんです
あなたが感じている、言いようのない寂しさ、虚しさ、そして時には怒りさえ伴うこの感情は、「予期グリーフ」という名前のある、ごく自然で当たり前の感情です。
この感情に気づき、名前を与えてあげるだけで、漠然としていた苦しみが少しだけ輪郭を帯び、扱いやすくなります。
「そうか、私は今、悲しんでいるんだ」と認識することが、グリーフケアの、そして自分を癒すための大切な第一歩です。
5-2. 予期グリーフとは?寄せては返す、喪失感の波
認知症グリーフは、一度にやってくるわけではありません。
物忘れがひどくなった時、徘徊が始まった時、自分のことを忘れられてしまった時、失禁するようになった時…。
何かを失うたびに、まるで寄せては返す波のように、何度も何度も悲しみが押し寄せてきます。
それは、まるで終わりのないお別れを、ずっと繰り返しているような感覚かもしれません。
5-3. 悲しみを、前に進む力に変える3つのステップ
この深い悲しみを、ただ耐え忍ぶのではなく、乗り越えていくためのステップがあります。
ステップ1:感情を認め、安全な場所で吐き出す
「悲しい」「寂しい」「辛い」…どんな感情も、決して否定せずに「そう感じているんだね」と、まずは自分で認めてあげましょう。
そして、安全な場所でその感情を吐き出すことが大切です。
日記に書きなぐる、信頼できる友人に電話で聞いてもらう、カウンセラーに相談する、認知症の家族会で分かち合う。
涙を流すことも、心を浄化する大切なプロセスです。
ステップ2:失われたものではなく、「今、ここにあるもの」に目を向ける
失われた能力や思い出ばかりに目を向けていると、悲しみは深まる一方です。
そうではなく、少しだけ視点を変えて、「今、ここにいる親」に目を向けてみませんか。
昔のように会話はできなくても、手を握れば温かい。
時折、ふと見せてくれる笑顔がある。
穏やかに眠っている寝顔がある。
失われたものを嘆き続けるのではなく、今ここに残されている愛おしい存在そのものに焦点を当てることで、新たな関係性を見出すことができるのです。
ステップ3:今の親と、新しい思い出を作る
昔の親とは違うかもしれません。
でも、今の親と、今のあなたで、新しい思い出を作ることはできます。
一緒に懐かしい歌を歌う、天気の良い日に縁側で日向ぼっこをする、好物のお菓子を「おいしいね」と言いながら一緒に食べる。
どんな些細なことでも構いません。
過去を懐かしむだけでなく、「今」を共に生きる喜びを見つけることで、あなたのグリーフは少しずつ癒されていきます。
5-4. 大丈夫、その感情を抱いているのは、あなた一人じゃありません
認知症の家族を介護する、ほとんどすべての人が、このグリーフを経験しています。
あなたは決して一人ではありません。
その悲しみは、あなたがこれまで、深く深く親を愛してきた、何よりの証なのです。
もう一人で抱え込まないで。社会とつながる、小さな勇気

ここまで、徘徊への対応、そしてご自身の心のケアについてお伝えしてきました。
最後の章では、あなたが一人で戦わなくて済むように、社会にある「つながり」についてお話しします。
助けを求めることは、決して恥ずかしいことでも、負けでもありません。
それは、あなたとあなたの大切な家族を守るための、最も賢明で、そして勇気ある選択なのです。
6-1. あなたの味方、専門家を頼るということ
介護の悩みが生まれたら、まず最初に思い出してほしい場所が「地域包括支援センター」です。
ここは、高齢者の暮らしを支えるための総合相談窓口。
保健師や社会福祉士といった専門家が、無料であなたの話を聞き、一緒に考えてくれます。
介護の専門家であるケアマネジャーという、あなたの最も身近な味方にも、ここで出会うことができます。
6-2. 「わかるよ」その一言に救われる。仲間とつながる場所
同じ悩みを抱える人と話すことは、時にどんな専門家のアドバイスよりも心に響くことがあります。
「認知症カフェ(オレンジカフェ)」は、認知症の人やその家族、地域の人々が気軽に集い、交流できる場所。
また、「認知症の人と家族の会」では、同じ立場の家族が集まり、悩みを分かち合い、支え合っています。
「辛いのは自分だけじゃなかったんだ」と感じるだけで、張り詰めていた心の糸が、ふっと緩むのを感じられるはずです。
6-3. 介護者が”休む”のは義務。心に余白を作るための賢い選択
介護者が休息を取ることは、贅沢ではなく、義務です。
罪悪感を感じる必要は一切ありません。
短期間施設に宿泊できる「ショートステイ」や、日帰りで施設に通う「デイサービス」といった介護サービスを賢く利用し、「介護から意識的に離れる時間」を作ってください。
心に余白が生まれて初めて、人は人に優しくできるのです。
まとめ:あなたは、あなたの人生の主人公であり続けていい

認知症の徘徊という、先の見えない暗闇。
その中で、あなたは今日まで、本当に、本当によく頑張ってこられました。
徘徊の原因を学び、対応法を実践することも、もちろん大切です。
しかし、それ以上に、何よりも忘れないでほしいこと。
それは、あなた自身が、あなたの人生の主人公であり続けることを、決して諦めないでほしい、ということです。
介護は、あなたの人生の一部ではあっても、全てではありません。
あなたは、親の介護者である前に、一人の、かけがえのない人間です。
笑う権利も、休む権利も、自分の幸せを追求する権利も、あなたには、ちゃんとあるのです。
だから、どうか自分を責めないでください。
一人で抱え込まないでください。
完璧を目指さないでください。
あなたの心が穏やかで、少しでも笑顔でいられること。
それが、巡り巡って、あなたの大切なご家族にとっても、一番の安心につながっていくのです。
この記事でお伝えした「自己肯定感」と「グリーフケア」という視点が、あなたの心を少しでも軽くし、明日へ向かうための一筋の光となることを、心から願っています。
あなたは、一人ではありません。
【関連記事】
親が認知症になったら…「昔の親はもういない…」その悲しみには名前があった。認知症介護の“絶望感”を“希望”に変えるグリーフケア
【自分らしい人生の終い方】40代から考える「よく死ぬ」ことは「よく生きる」こと。自己肯定感の専門家と学ぶ、終活の新しいかたち
【グリーフケア専門記事】看取りの後に感じる「もっとこうすれば…」の気持ちとどう向き合う?心の整理法とアドバイス

自己肯定感の第一人者である中島 輝と共に、自己肯定感の重要性を多くの人に伝えるために活動中。講師としての登壇経験が多く、自己肯定感をはじめとするセラピー・カウンセリング・コーチングの知識が豊富。メディアサイト「自己肯定感ラボ」を通じ、誰もが輝いて生きていくための情報を発信中。

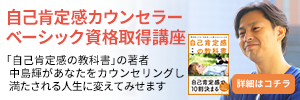
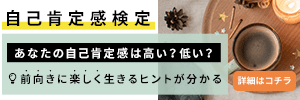
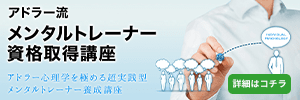
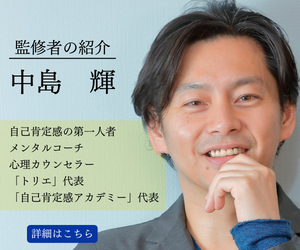
コメント