すやすやと眠る愛犬の寝顔。
その穏やかな表情を見ていると、思わず抱きしめたくなったり、名前を呼んで起こしたくなったりするかもしれません。しかし、老犬にとって「睡眠」は、若い頃よりもはるかに大切な時間です。加齢とともに心身の変化が進む老犬にとって、安らかな眠りは心身の回復に不可欠であり、その眠りを妨げることは、かえって愛犬に負担をかけてしまう可能性があります。
この記事では、老犬を深く愛するあなたに、寝ている老犬に「やってはいけないこと」と、愛犬との穏やかな時間を守るための「正しい見守り方」をお伝えします。
「寝ている老犬にやってはいけないことは?起こすべきタイミングも解説」という記事でも触れられているように、老犬との暮らしには、これまでとは異なる配慮が必要です。愛犬への深い愛情ゆえに、知らず知らずのうちに負担をかけてしまっていた、と自分を責めてしまう必要は全くありません。自己肯定感を育み、愛犬との別れに備えるグリーフケアの視点を取り入れることで、あなたは愛犬との残された時間を「後悔のない、かけがえのない宝物」に変えることができるでしょう。
さあ、私たちと一緒に、愛犬との穏やかな日々をデザインしていきましょう。
なぜ老犬の睡眠は特別に大切なのか
愛犬が年を重ねるにつれて、「寝ている時間が増えたな」と感じる飼い主さんは多いのではないでしょうか。老犬にとって睡眠は、若い頃とは異なる重要な意味を持っています。その理由を理解することで、私たちは愛犬の安らかな眠りをより深く守ることができるようになります。
🐾 老犬の睡眠サイクルと心身の変化
老犬は、若い犬に比べて睡眠時間が長くなる傾向があります。これは、加齢とともに体力が低下し、疲労回復により多くの時間を必要とするためです。また、睡眠の質も変化します。
- 深い眠りの減少: 浅い眠りが増え、物音やちょっとした刺激で目覚めやすくなります。これにより、熟睡感が得られにくくなることがあります。
- 夜間覚醒の増加: 認知症の症状や排泄間隔の短縮などにより、夜中に何度も起きて鳴いたり、動き回ったりすることがあります。
- 感覚の変化: 視力や聴力が低下するため、人が近づいていることに気づきにくくなり、急に触られると驚いてしまうことがあります。
「寝ている老犬にやってはいけないことは?起こすべきタイミングも解説」という記事でも、睡眠時の老犬が敏感であることが指摘されています。こうした心身の変化を理解することが、愛犬との穏やかな共生のために不可欠です。
🐾 睡眠不足が老犬にもたらす影響
人間と同様に、老犬にとっても睡眠不足は深刻な健康問題を引き起こす可能性があります。
- 認知症の悪化: 十分な睡眠が取れないと、脳の疲労が蓄積し、認知症の症状が悪化する可能性があります。
- 免疫力の低下: 睡眠不足は免疫機能を低下させ、病気にかかりやすくなったり、回復が遅れたりする原因となります。
- ストレスの増加: 安眠できない日々は、愛犬に大きなストレスを与えます。ストレスは問題行動(無駄吠えや徘徊など)を引き起こし、飼い主さんの心にも負担をかけます。
- 体力の回復の遅れ: 筋肉や関節の回復が遅れ、足腰の弱体化や床ずれのリスクを高めることにもつながります。
- 心の安定の欠如: 睡眠が不十分だと、精神的に不安定になりやすく、不安感や警戒心が強まることがあります。
愛犬の健やかな老後を支えるためには、質の高い睡眠を確保してあげることが、飼い主さんのできる大切なケアの一つなのです。
寝ている老犬に「やってはいけないこと」【5つの注意点】

愛犬を深く愛するからこそ、ついついやってしまいがちな行動が、実は老犬にとっては大きなストレスになっていることがあります。「寝ている老犬にやってはいけないことは?起こすべきタイミングも解説」の記事も参考に、特に注意すべき5つのポイントを確認しましょう。
1. むやみに触る・撫でる
愛犬の寝顔が愛おしくて、つい頭や体を撫でたくなりますよね。しかし、寝ている老犬を急に触ることは、大きな負担となる可能性があります。
- 驚かせてしまう: 視力や聴力が衰えている老犬は、人が近づいていることに気づきにくいため、急に触られるとびっくりして飛び起きたり、興奮したりすることがあります。
- 熟睡を妨げる: 浅い眠りの時に触られると、せっかくの深い眠りに入るチャンスを奪ってしまいます。
- 警戒心を高める: 突然の刺激は、老犬の警戒心を高め、安心して眠れない状況を作り出す可能性があります。
もし撫でてあげたい場合は、まずはゆっくりと近づき、声をかけるなどして愛犬が起きていることを確認してから、優しく触れてあげましょう。寝ている間に撫でてしまって愛犬が眠ってしまった場合は、そのまま優しく撫で続け、少し経ったらそっと離れてあげることが大切です。
2. 名前を呼ぶ・声をかける
寝ている愛犬に、可愛いからといって名前を呼んだり、話しかけたりすることも避けましょう。
- 起こしてしまう: 名前を呼ばれれば、老犬は反応して起きてしまうことがあります。特に聴力が低下している場合は、大きな声で呼ばれることで、より一層驚かせてしまうかもしれません。
- 認知症への影響: 認知症の老犬は、急に起こされることで混乱したり、不安になったりすることがあります。
愛犬が安らかに眠っている時は、そっと見守り、静かな環境を保ってあげることが何よりも大切です。
3. 大きな音を立てる・騒がしくする
老犬のいる部屋で、大きな音を立てる、テレビの音量を上げる、掃除機をかける、子供が騒ぐといった行為も、愛犬の安眠を妨げます。
- 安心できない環境: 音に敏感な犬にとって、騒がしい環境は安心して眠れない状況を作り出します。
- ストレスの蓄積: 睡眠中に何度も起こされることで、愛犬にストレスが蓄積し、体調不良や問題行動につながる可能性があります。
愛犬が寝ている間は、できるだけ静かな環境を心がけましょう。もし掃除をする必要がある場合は、愛犬が起きている時間帯や、別の部屋で寝ている時に行うなどの工夫が必要です。
4. 急に起こす・抱き上げる
排泄のために、あるいは可愛さのあまり、寝ている老犬を急に起こしたり、抱き上げたりすることも避けましょう。
- 関節への負担: 老犬は足腰が弱くなっているため、急に抱き上げられると、関節に負担がかかったり、痛がったりすることがあります。
- 平衡感覚の乱れ: 眠りから覚めたばかりの老犬は、平衡感覚が一時的に不安定になることがあります。急に抱き上げられることで、落下のリスクも高まります。
- 混乱や不安: 認知症の老犬は、急な状況の変化に混乱しやすいため、寝起きに急に抱き上げられると、不安を感じてしまうことがあります。
もし起こす必要がある場合は、ゆっくりと声をかけ、愛犬が自分で起きるのを待ってから、優しくサポートしてあげましょう。
5. 寝ている場所を急に変える
老犬は環境の変化に敏感です。特に、寝床は愛犬にとって最も安心できる場所であるため、急に場所を変えることは大きなストレスになります。
- 不安感の増大: 慣れない場所で眠ることは、愛犬に不安感を与え、質の良い睡眠を妨げます。
- 居場所の認識の混乱: 認知症の老犬は、自分の居場所を認識する能力が低下しているため、寝床を急に変えられると混乱してしまうことがあります。
どうしても寝床を移動させる必要がある場合は、愛犬が起きている時に、ゆっくりと新しい場所に慣らさせてあげましょう。
「起こすべきタイミング」と「正しい起こし方」

寝ている老犬には、むやみに手を出さないことが大切ですが、時には愛犬のために起こしてあげなければならないタイミングもあります。そのような時に、どのようにすれば愛犬に負担をかけずに起こせるのかを知っておきましょう。
🐾 どんな時に起こすべき?老犬が発するサイン
愛犬の健康と安全を守るため、以下のようなサインが見られたら、優しく起こしてあげることを検討しましょう。
- 排泄の兆候: もじもじしている、落ち着きがない、お尻を気にしているなどのサインが見られたら、排泄を促してあげる必要があります。特に、普段の排泄時間と重なる場合は注意が必要です。
- 長時間同じ姿勢で寝ている: 寝たきりの老犬の場合、長時間同じ姿勢でいると床ずれの原因になります。「寝ている老犬にやってはいけないことは?起こすべきタイミングも解説」の記事でも、床ずれ防止のために2~3時間おきに寝返りをさせてあげることが推奨されています。
- 体勢が苦しそう: いびきがひどい、呼吸が乱れている、苦しそうな体勢でいるなど、明らかに不調が見られる場合は、体勢を直してあげたり、獣医さんに相談したりする必要があります。
- 痙攣や発作: 眠っている間に手足をバタバタさせる、体が震えるなどの痙攣や発作が見られた場合は、周囲の危険なものを遠ざけ、落ち着いて様子を見ましょう。ただし、てんかんなどの発作の場合は、慌てて触ったり、大声で呼んだりしてはいけません。発作の様子を動画で撮影し、獣医さんに相談することが大切です。
- 食欲不振や水分補給の不足: 長時間寝ていて、食事や水分を摂る機会がないと、脱水症状や栄養不足につながることがあります。
これらのサインを見逃さないためにも、日頃から愛犬の様子をよく観察し、小さな変化に気づけるように心がけましょう。
🐾 愛犬に負担をかけない「優しい起こし方」
やむを得ず愛犬を起こす必要がある場合は、愛犬にストレスを与えないよう、以下の点に注意して優しく起こしてあげましょう。
- ゆっくりと声をかける: まずは静かに愛犬の名前を呼んだり、優しく話しかけたりして、愛犬が自ら目を覚ますのを待ちましょう。
- 優しく体に触れる: 声かけに反応がない場合は、そっと体に触れて、ゆっくりと揺り起こすように促します。急に体を強く掴んだり、揺らしたりすることは避けましょう。
- 明るさを調整する: 部屋の電気を少し明るくしたり、カーテンを開けて自然光を取り入れたりすることで、愛犬が目覚めやすい環境を作ります。
- 食事や排泄を促す: 愛犬が目覚めたら、食事や水分補給、排泄を促すために優しく誘導してあげましょう。必要であれば、排泄補助やおむつの交換を行います。
- 焦らせない: 老犬は行動がゆっくりになるため、焦らせたり、急かしたりすることは避けましょう。愛犬のペースに合わせて、優しくサポートしてあげることが大切です。
愛犬への深い愛情と、老犬の心身への理解が、愛犬との穏やかな時間を築く上で何よりも重要です。
自己肯定感で育む、愛犬と飼い主の心穏やかな関係

老犬の介護や見守りは、飼い主さんにとって精神的な負担となることも少なくありません。愛犬のためにと頑張りすぎるあまり、自分を追い詰めてしまい、自己肯定感が揺らいでしまうこともあります。しかし、愛犬との残された時間を心穏やかに過ごすためには、まずあなた自身の心のケアが不可欠です。
🐾 「完璧な飼い主」を手放す勇気
あなたは、愛犬のために常に完璧なケアをしようと頑張っていませんか?
- 「もっとできるはずなのに…」
- 「他の飼い主さんはもっとちゃんとやっているのに…」
- 「私がもっと〇〇だったら…」
このような思いは、あなたが愛犬を深く愛しているからこそ生まれるものです。しかし、この「完璧でなければならない」というプレッシャーが、あなた自身の自己肯定感を下げ、心身を疲弊させてしまう原因になることがあります。
老犬介護に「完璧」はありません。愛犬の状況は日々変化し、その変化に対応することは、時には困難を伴います。だからこそ、「できる範囲で大丈夫」「今の私で十分」と、自分に許可を与えてあげる勇気を持ちましょう。
ある記事でも「介護の家程で起こることの全てに責任を感じる必要はなくできる範囲でのケアをすることが重要」であると述べられています。あなたの心が穏やかであることが、愛犬にとって何よりの幸せなのです。
🐾 「できていること」に目を向け、自分を褒める
自己肯定感を育むためには、日々の小さな「できていること」に意識的に目を向け、自分を褒めてあげることが大切です。
- 愛犬のためにできたこと: 今日、愛犬にごはんをあげられた、おむつを交換できた、優しく撫でてあげた、など、どんなに些細なことでも構いません。
- 自分自身のためにできたこと: 少し休憩できた、温かいコーヒーを飲んだ、ゆっくりと呼吸する時間を持てた、など、自分を労わる行動も大切です。
「寝ている老犬にやってはいけないことは?起こすべきタイミングも解説」という記事でも、「どんな些細なことでもできたら褒めてあげてください」とあります。小さな達成感を積み重ねることで、あなたの心は少しずつ満たされていきます。
🐾 【ワーク】愛犬の寝顔から「心の平和」を見つける
静かな場所で、愛犬の寝顔を眺める時間を作ってみましょう。
- 愛犬が安らかに眠っている姿を見て、どんな感情が湧いてきますか?
- その寝顔を見ている時、あなたの心はどんな状態ですか?
- 愛犬が安心しているのは、誰のおかげだと思いますか?
- あなた自身が、愛犬のために「今、できていること」は何ですか?(どんなに小さなことでも構いません)
このワークを通じて、あなたが愛犬に与えている大きな愛情と、それによって得られる愛犬の安らぎを感じ取れるはずです。そして、その愛は、あなたの自己肯定感を温かく満たしてくれるでしょう。
予期グリーフと向き合い、愛犬との「今」を大切にする
老犬との暮らしは、愛犬の旅立ちが近づいていることを意識せざるを得ない期間でもあります。この「いずれ来る別れ」に対する悲しみや不安は、「予期グリーフ」と呼ばれ、飼い主さんの心を深く揺さぶります。
🐾 「いずれ来る別れ」への悲しみを受け入れる
予期グリーフは、まだ実際に喪失が起こっていないにもかかわらず、それが起こることを予期して感じる悲しみ、不安、怒り、無力感などの感情です。「もっと一緒にいたい」「このままいなくならないでほしい」と願う一方で、「早く楽になってほしい」と矛盾する感情が芽生え、自分を責めてしまうこともあります。
このような複雑な感情を抱えることは、愛犬を深く愛している証拠です。自分を責める必要は全くありません。大切なのは、これらの感情を否定したり、押し込めたりせず、ありのままに感じ、向き合うことです。
🐾 グリーフケアが教えてくれる、心の準備と癒し方
グリーフケアは、大切なものを失った人がその悲しみを乗り越え、回復していく過程をサポートするものです。予期グリーフにおいても、その考え方は非常に有効です。
- 感情を表現する: 悲しい、辛い、怖い、といった感情を言葉にしたり、日記に書いたり、信頼できる人に話したりすることで、心の中に溜め込まずに解放することができます。
- 愛犬との思い出を振り返る: 愛犬との出会いからこれまでの楽しい思い出を振り返る時間は、愛犬への感謝の気持ちを再確認し、今の介護がどれほど大切な時間であるかを感じさせてくれます。
- 「今」を大切にする: 「いつか来る別れ」を恐れるあまり、「今」愛犬と過ごせる時間を十分に味わえないことがあります。グリーフケアは、「今、この瞬間」愛犬にできること、愛犬との触れ合いを大切にすることへと意識を向けさせてくれます。愛犬が喜ぶこと、心地よいと感じることをしてあげましょう。
- 心の準備をゆっくりと進める: 別れは避けられない現実です。心の準備には時間が必要です。焦らず、自分のペースで、愛犬との別れを受け入れる心のスペースを作っていくことが大切です。
- 自分を責めない: 愛犬の病気や老衰は、あなたのせいではありません。できる限りのことをしている自分を認め、労ってあげましょう。
グリーフケアは、愛犬との絆を再確認し、未来への不安を和らげ、「今」をより深く愛する力を与えてくれるでしょう。
変化を受け入れ、自分らしく生きる力を育む
グリーフケア心理カウンセラー
ベーシック資格取得講座
愛犬との別れに備える予期グリーフと向き合い、心の平穏を取り戻したいあなたへ。
グリーフケアの専門的な知識と実践を学び、あなた自身の心の回復を促し、さらには大切な人の支えとなれる力を身につけませんか?
本講座では、自己肯定感を基盤としたグリーフケアを学ぶことができます。変化を恐れず、未来への希望を育むための第一歩を、私たちと一緒に踏み出しましょう。
【開催日程】
- 2025年11月20日
- 2025年12月27日
- 2026年1月24日
老犬との心地よい暮らしのための環境づくり

老犬が安心して快適に眠り、穏やかに過ごせる環境を整えることは、愛犬の心身の健康だけでなく、飼い主さんの介護負担の軽減にもつながります。
🐾 安心して眠れる「安全な寝床」のポイント
「寝ている老犬にやってはいけないことは?起こすべきタイミングも解説」の記事にもあるように、老犬にとって安全で安心できる寝床は非常に重要です。
- 静かで落ち着ける場所: 家族の出入りが少なく、大きな物音や光の刺激が少ない場所に寝床を設置しましょう。
- 温度・湿度管理: 季節に合わせて、室温や湿度を適切に保ちましょう。特に冬場は暖かく、夏場は涼しく快適に過ごせるように配慮が必要です。
- 体を支える寝具: 硬すぎず、柔らかすぎない、体圧分散性の高いマットやクッションを選びましょう。床ずれ予防にもつながります。
- 清潔を保つ: 寝具はこまめに洗濯し、清潔に保ちましょう。排泄の失敗があった場合は、すぐに拭き取り、消臭することが大切です。
- 囲われた空間: 老犬は視力や聴力が衰えるため、四方を囲まれたケージやクレート、ドーム型ベッドなど、安心できる空間を用意してあげると良いでしょう。
🐾 日常生活で心がけたいこと
老犬との心地よい暮らしのためには、日々の生活習慣にも配慮が必要です。
- 規則正しい生活リズム: 食事や散歩、睡眠の時間をできるだけ一定にすることで、愛犬は安心して過ごせるようになります。
- 無理のない散歩と運動: 足腰の負担を考慮し、短い時間で複数回、平らで滑りにくい場所を選んで散歩させましょう。抱っこ散歩やカートを利用するのも良い刺激になります。
- 適度なマッサージ: 血行促進や関節のケアのために、優しくマッサージをしてあげましょう。ただし、病気や炎症がある場合は獣医さんに相談してから行ってください。
- 話しかける時の配慮: シニア犬は目や耳が悪くなり、人が近づいても気が付かないことがあります。前からゆっくり近づいたり、優しく声をかけてから触れるなど、配慮をしましょう。
- 栄養バランスの取れた食事: 消化吸収の良い老犬用のフードを与え、食事台で高さを調整して食べやすくするなど、工夫しましょう。
これらの配慮は、愛犬の心身の負担を減らすだけでなく、飼い主さんの心にもゆとりをもたらしてくれるでしょう。
老犬の認知症と向き合うあなたへ:遊びが織りなす「希望」と「自己肯定感」で愛犬と笑顔の毎日をhttps://ameblo.jp/info-ebisutsukuba-color/entry-12934983952.html?frm=theme
老犬のトイレ失敗で自分を責めてしまうあなたへ|自己肯定感&グリーフケアで愛犬との最期の時間を宝物に変えるhttps://ameblo.jp/info-ebisutsukuba-color/entry-12920375057.html?frm=theme
愛犬との「最期の時間」を後悔なく過ごすために

老犬との日々は、いつか必ず来る別れの時へと向かっています。その「最期の時間」を後悔なく、愛と感謝に満ちたものにするためには、心の準備と具体的な行動が大切です。これは、愛犬との絆を再確認し、感謝を伝える尊い時間でもあります。
🐾 「ありがとう」で見送る準備
「ありがとう」の気持ちで愛犬を見送ることは、あなた自身のグリーフケアにもつながります。
- 愛犬との「バケットリスト」を作る: 愛犬との残された時間で、一緒に何をしたいですか? 行きたい場所、食べさせたいもの、してあげたいことなどをリストアップし、一つずつ叶えていくことで、後悔のない時間を過ごせるでしょう。
- 旅立ちの準備: どのような形で愛犬を見送りたいのか、事前に家族と話し合い、情報を集めておきましょう。火葬、土葬、合同葬など、様々な選択肢があります。愛犬にとって、そしてあなたにとって最善の形を検討することが大切です。
- 愛犬への感謝を伝える時間: 日々、愛犬に「ありがとう」「大好きだよ」と伝える時間を大切にしましょう。言葉だけでなく、優しく撫でたり、抱きしめたり、一緒に静かに過ごす時間そのものが、愛と感謝の表現になります。
- 自分の心のケア: 愛犬を失った後の「グリーフ」は、想像以上に深く、長く続くことがあります。事前に心のケアの方法を学んだり、サポートしてくれる人を見つけておくことも大切です。専門家やグリーフケアの講座を利用することも、心の回復を助ける大きな力となります。
「後悔しないペットの埋葬」とは、単なる物理的な準備だけではありません。それは、愛犬との全ての時間を肯定し、「ありがとう」の気持ちで締めくくるための、心の旅路なのです。
後悔しないペットの埋葬 愛犬を「ありがとう」で見送るためのグリーフケアと7つの選択肢https://ameblo.jp/info-ebisutsukuba-color/entry-12923633832.html?frm=theme

自己肯定感の第一人者である中島 輝と共に、自己肯定感の重要性を多くの人に伝えるために活動中。講師としての登壇経験が多く、自己肯定感をはじめとするセラピー・カウンセリング・コーチングの知識が豊富。メディアサイト「自己肯定感ラボ」を通じ、誰もが輝いて生きていくための情報を発信中。

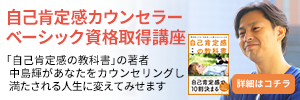
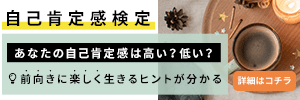
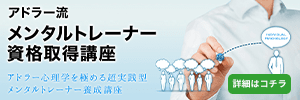
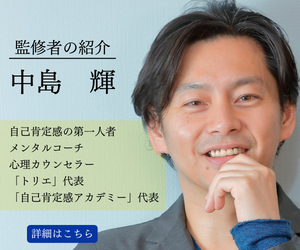
コメント